【防府市】三田尻御舟倉跡の基本情報・アクセス・写真情報
本記事では山口県防府市にある「三田尻御舟倉跡」について紹介しています。所在地などの基本的な情報や、写真、アクセス情報などをわかりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてください。
三田尻御舟倉跡の概要・写真情報
三田尻御舟倉跡は、山口県防府市三田尻にある萩藩の水軍(毛利水軍)の本拠地跡です。萩往還関連遺跡として国指定史跡となっています。
現在では通堀(かよいぼり)と、これに通じる船入水路の一部を残すのみとなっていますが、当時は藩主の御座船や軍船が常置され、船の建造や修理ができる設備も整えられていました。
三田尻御舟倉の変遷
三田尻御舟倉の起源
関ヶ原合戦の後、防長二カ国に減封(所領や城・屋敷の一部を削減する刑罰)となった毛利氏は萩に居城を置くことにしました。(元々は広島城を拠点としていました)
慶長9年(1604)に萩城を築いたのち、毛利氏は参勤交代での「御成道(おなりみち)」として萩城から瀬戸内海(三田尻)までをほぼ一直線で結ぶ道「萩往還(はぎおうかん)」を整備します。
下松(くだまつ)に置かれていた御舟倉(水軍本拠地)を三田尻に移しました。参勤交代の一行はここで船に乗り換え海路で大阪を目指しました。
また、船手組(ふなてぐみ)という船舶の管理や海上巡視などにあたった組織が置かれ、軍の任務、人や物資の輸送などを行っていました。
幕末の三田尻御舟倉
三田尻御舟倉は1863年に廃止され、この地には「海軍局」が置かれました。
その後、三田尻御舟倉は1865年の功山寺挙兵(高杉晋作ら正義派の長州藩諸隊が、保守派打倒のために下関市長府にある功山寺で起こしたクーデター)の舞台として一部登場します。
高杉らは下関新地にある萩藩の会所を急襲し、資金と食料を得たのち、三田尻の海軍局を訪れ佐藤与蔵らを説き伏せ、萩藩所有の洋式軍艦3隻全てをクーデター軍側に引き入れました。
この内乱の結果、主導権を握っていた保守派を破って長州を再び討幕へと導くことになります。
現在の三田尻御舟倉
明治以降に建物の解体や堀の埋め立てが進み、御舟倉の往時の姿をとどめるのは通堀(かよいぼり)と、これに通じる船入水路の一部のみとなりました。
萩藩の命により鋳造された梵鐘が、三田尻御舟倉の時鐘として使用されていましたが御舟倉の廃止により、由縁ある「大楽寺」に移されています。


2-320x180.jpeg)
三田尻御舟倉跡の基本情報
三田尻御舟倉跡の住所や連絡先などの基本情報を掲載しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 三田尻御舟倉跡 みたじりおふなぐらあと |
| 所在地 | 〒747-0814 山口県防府市三田尻3-3-13 |
| 問い合わせ先 | 0835-25-2237(文化振興課) |
| 駐車場 | – |
三田尻御舟倉跡のアクセス・MAP情報
三田尻御舟倉跡の周辺スポット
三田尻御舟倉跡の周辺には以下のようなスポットがあります。
観光スポット
2.jpeg)












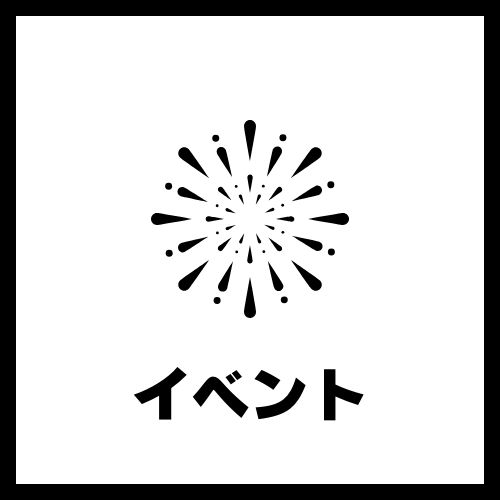






5.jpeg)



